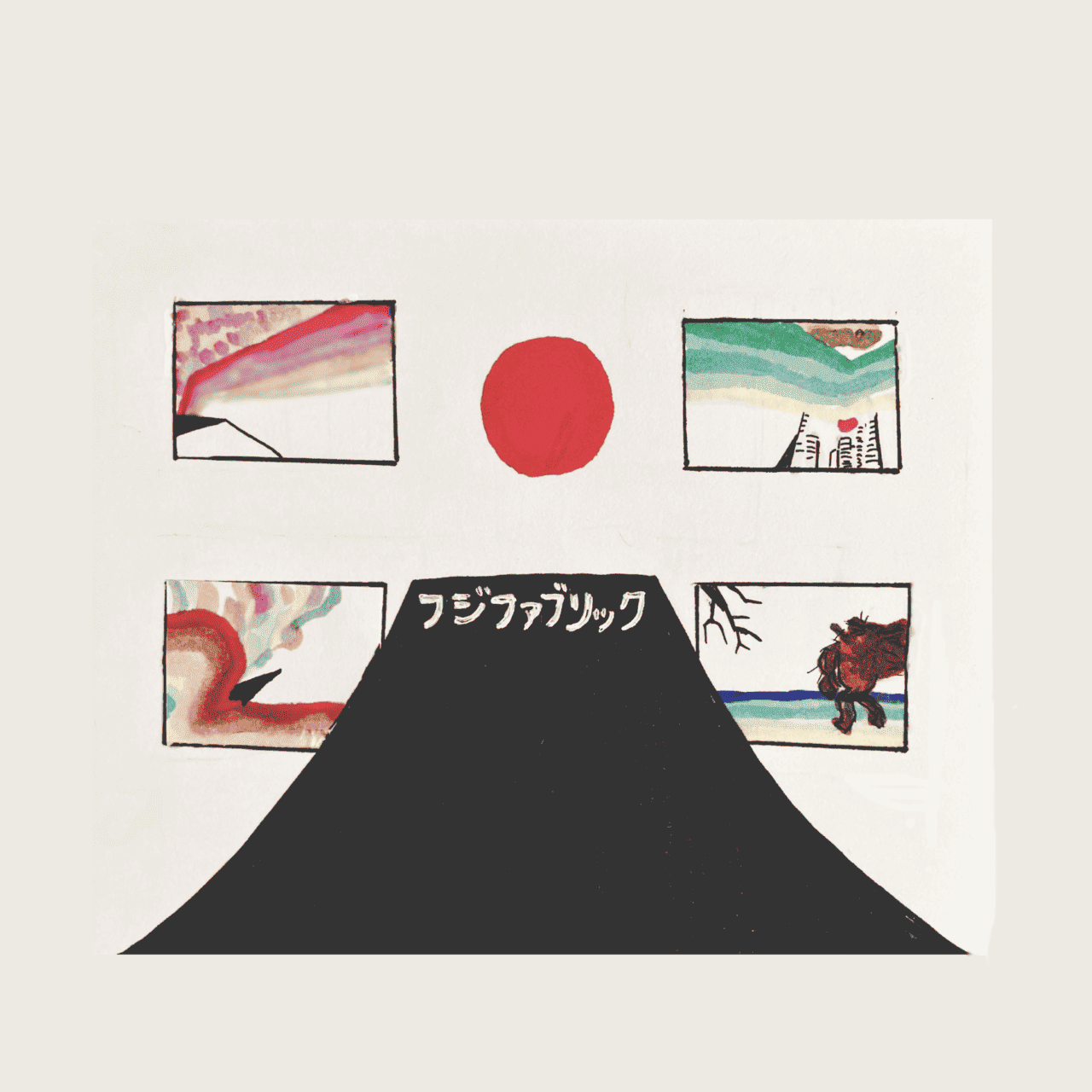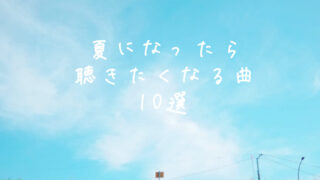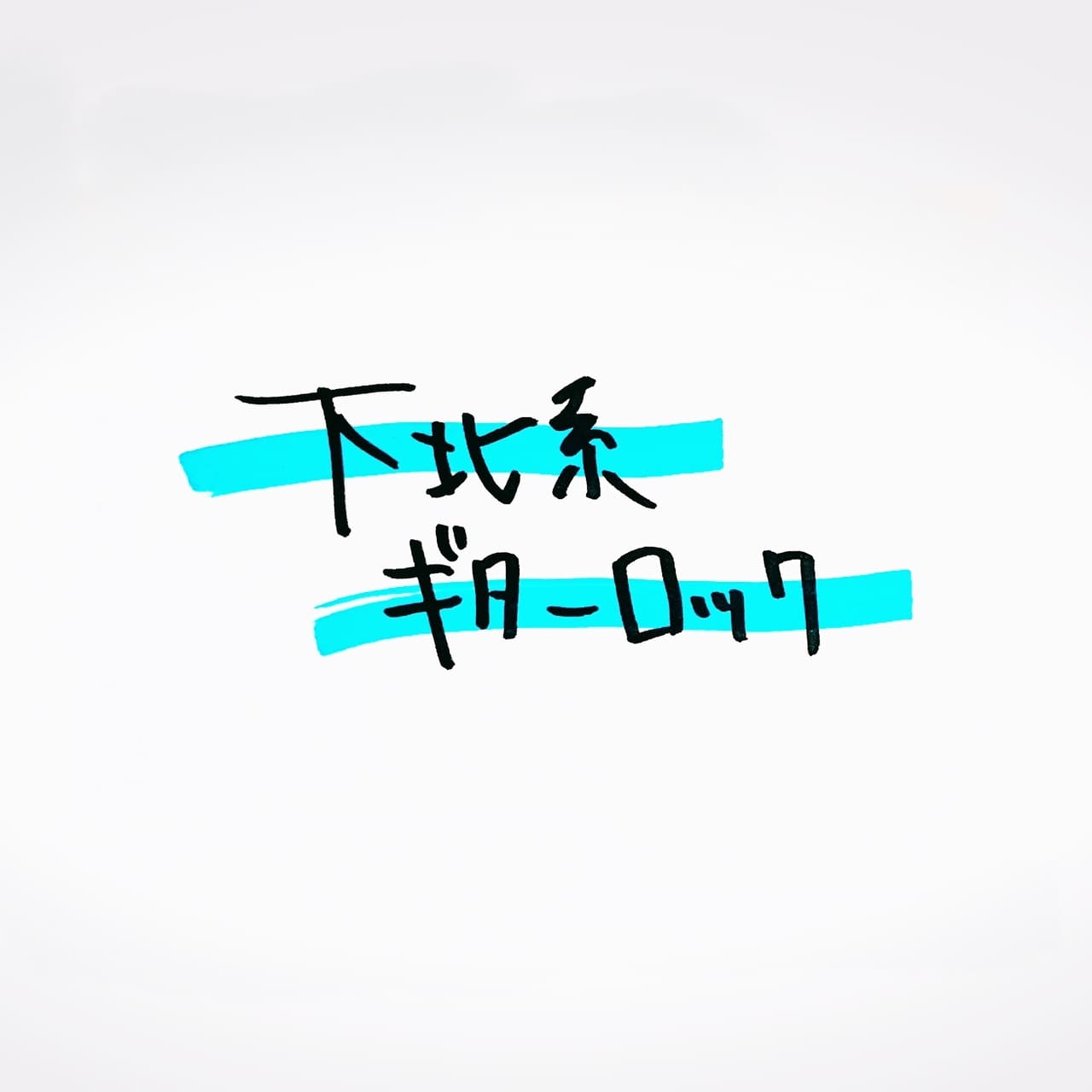2025年2月をもって活動休止を発表した日本のロックバンド、フジファブリック。
2009年にギターボーカル志村正彦の急死、メンバー3人での活動継続の決定など、波瀾万丈な道のりを歩んできました。彼らなりの答えを見つけ、突き進んできた2000年結成からの25年間。
バンド自身にとってもファンにとっても作品ひとつひとつに並々ならぬ思い入れがあるバンドだと言っても過言ではないでしょう。

今回は日本のバンドらしさあふれる叙情的なロックが魅力のフジファブリックならではの粋なリリース形態『四季盤』について徹底解説していくよ。
フジファブリックとは
叙情的なメロディと度肝を抜かれる展開。高い演奏技術に裏付けされた予測不可能かつ多彩な表現で、独自の世界を構築する日本のロックバンド、フジファブリック。
2000年に山梨県富士吉田市にてギターボーカル・志村正彦を中心に結成。インディーズ時代からメンバーチェンジを重ね、2004年に志村正彦(Vo/G)、加藤慎一(B)、金澤ダイスケ(Key)、山内総一郎(G)、足立房文(Dr)の5人体制でメジャーデビューしました。四季をテーマにした連作シングル第一弾「桜の季節」がメジャーデビューシングルとなります。その後、2ndアルバム『FAB FOX』リリースした翌春、2006年3月にドラムの足立が脱退し、四人編成での活動になりました。
そして、2009年12月24日にギターボーカルでありフジファブリックの核でもあった志村正彦が急逝。後に、残されたメンバーである山内総一郎、加藤慎一、金澤ダイスケの3人体制で活動を継続してきましたが、2025年2月をもって活動休止を発表。志村が亡くなってからは15年、結成からは25年という長い月日、フジファブリックというバンドを守り続けてくれていたことで、3人体制での多くの名曲たちは勿論のこと志村正彦が遺した名曲たちも当時を知らない人たちにまで多く愛されることとなったのではないかと感じています。
フジファブリック「四季盤」とは
ファンに愛され続けてきたフジファブリックを語る上で欠かせない作品は多数ありますが、その中でもフジファブリックならではのコンセプトでリリースされているのが「四季盤」です。
2004年4月にメジャーデビューをすることになるフジファブリックですが、メジャーデビューシングルからの4作品を日本の四季・春夏秋冬をテーマにしたシングル連作リリースにて発表しました。2004年4月にはメジャーデビューシングルとして春盤「桜の季節」を発売。同年7月には夏盤「陽炎」を、同年9月に秋盤「赤黄色の金木犀」をリリース。そして翌年の2005年2月には冬盤「銀河」がリリースされ、この4作品の総称を「四季盤」と呼びます。
リリース月を見ていただくと分かるように、実際の季節に応じた盤がリリースされているのも、日本の四季や叙情的な風景を克明に描写するフジファブリックならではの粋な計らいが感じられます。よりその楽曲の解像度を高められると同時に、一年毎に必ず繰り返される四季を過ごしていく中で記憶に結びつき、ふと想い起こされる楽曲になっているのではないでしょうか。
春盤「桜の季節」
四季盤の中でも「春盤」にあたるのが、2004年4月14日に発売された1stシングル『桜の季節』。
『桜の季節』は記念すべきメジャーデビュー・シングルでもあります。
特徴的なイントロと鮮烈な印象を残すギターリフ。イントロが流れたその瞬間、舞う花びらを巻き込んだ春の強い風が眼前に吹かれたような衝撃に襲われます。桜の季節は端的に言うと「別れを受け入れて去り行くあの人へ手紙を書こう」という内容の歌ですが、そこに変な小細工や泣かせにかかる表現がないのがフジファブリックらしさ溢れてて良いところ。桜の季節は全編を通して淡々としており、“やるせない”という感情に帰結するのが曲の物悲しさを一層際立たせていると感じます。そんな歌詞がボーカルの志村正彦の朴訥とした歌い方とマッチして絶妙な哀愁を醸し出しているのです。
フジファブリックはCメロ1が非常に美しいバンドですが、桜の季節のCメロも至高です。(※フジは楽曲構成が複雑なためどこをCメロとするかは諸説ありそうですが、こちらでは下記の引用部分をCメロとします)
美しいキーボードの旋律、景色が流れていくようなギターリフが印象的な中盤の間奏の後、“ 坂の下 手を振り 別れを告げる ” とCメロに入っていくのですが、刻むような歌唱とどことなく不安感が漂うリズムの中、焦燥感が掻き立てられていき “ 心に決めたよ ” の最後のロングトーンでサビへ繋がっていくのがドラマチック。まさに一本の映画を見たような気分にさせられます。
ならば愛を込めて
フジファブック「桜の季節」
手紙をしたためよう
作り話に花を咲かせ
僕は読み返しては 感動している!
“ならば”“手紙を”の前のOh,Soの部分が、一番ではカットアウト/ディレイで演出されているのに対して、ラスサビ前のOh,Soはロングトーンなのもこの曲の好きなところ。気持ちの昂りを感じます。
そしてこの曲で最も志村正彦らしさを個人的に感じているのが、上記の歌詞の後半部分。しばしば志村の歌詞は妄想を膨らませて描かれており、それが唯一無二の魅力のひとつですが、作り話に花を咲かせた手紙を自身で読み返し感動している、という部分はある種の狂気を孕みながら感傷に耽っている行為とも取れます。別の見方としては深読みになりますが、この楽曲そのものを手紙となぞらえることも出来そうだなとも感じました。
サビに始まったこの楽曲はまたサビへと戻り、美しいアウトロにて終幕。花が咲き、散り、過ぎ去っていく桜の季節の美しいだけじゃない物悲しさを見事に表現しきった、春盤を名乗るにふさわしい名曲です。
フジファブリックのミュージックビデオは映像作家のスミス監督が手がけていることが多く、四季盤も全てそうなのですが、「桜の季節」の制服を着た少女も楽曲に合っていて非常に良いMVだと感じます。“桜の季節”という答えを導き出すためのテスト中の妄想だった、という物語性もフジファブリックの楽曲の世界観にマッチしていて素敵でした。
カップリング曲の「桜並木、二つの傘」はインディーズ期の1stミニアルバム『アラカルト』にも収録されている名曲であり、同じ桜をテーマにしているものの、「桜の季節」よりもどことなく陰鬱さを感じられる変態的なダンスナンバーに仕上がっています。奇天烈なメロディラインなのに、叙情的で鮮烈な風景が浮かぶような、志村正彦ならではの言い回しで表現された歌詞が見事な1曲です。
夏盤「陽炎」
四季盤において「夏盤」は、2004年7月14日発売の2ndシングル『陽炎』です。
「陽炎」はその名の通り夏、しかも湿度の多い日本の夏の中で見た世界を描いた楽曲です。
この曲からは、幼少期の志村少年が駆け回っている光景と同時に、現在地点から思い返して歌にしている志村正彦の等身大の存在を感じられます。こういったノスタルジーは誰もが持っているもので、その豊かな情景描写で曲の中に没入させてくれます。
志村正彦は山梨県富士吉田市の出身です。偶然にも私も山梨出身なので「陽炎」の風景描写が克明すぎるゆえに、自分の幼少期をいつも思い出します。富士吉田市は私が幼少期を過ごした盆地よりも標高が高いので幾分か涼しかったのではないかなと思いますが、山に囲まれている山梨県は、暑い夏の午後には夕立が降りやすいのです。山梨県を含む日本の田舎の風景の中にある、夏の夕立、民家の路地裏、雨が上がり直射日光が照りつけ、陽炎が揺れている光景。立ちこめる湿度の多い夏の香りと共に幼少期の自分が思い起こされざるを得ない情景描写に胸がいっぱいになります。
「陽炎」は疾走感のあるギターロック曲であると同時に、屈指の鍵盤曲であるとも感じます。
ライブでは「キーボード、金澤ダイスケ」の紹介と共に始まるキーボード・ソロに何度痺れたことか!と共感を求めたいくらいに、陽炎のキーボード・ソロがカッコ良すぎる。美しい旋律をロックに弾かせたら右に出るものはいないんじゃないか?と思うほどに、フジファブリックというバンドに不可欠な演奏がここにあります。間奏のギターソロとアウトロのキーボードが秀逸すぎる、と別の記事(※夏になったら聴きたくなる曲10選)でも語りましたが、何度でも言わせてほしい。ぜひ注目して聴いていただきたいです。
ミュージックビデオではギターソロが巻き戻されていたり、時計の針が過去に戻ったりまた動き出したりする演出が、この曲の現在地点から幼少期の体験の中へ引き戻される感覚とリンクしているように思えます。感覚的なところだけ演出に落とし込んでいて、歌詞の世界をそのまま表現しようとしていないところがこのMVの好きなところ。
そしてカップリング曲は『NAGISAにて』。こちらはアルバム未収録の楽曲で、後々FAB BOXのB面集にリマスタリングされ収録されているのみの貴重な楽曲。ライブでは時折披露されているため、ライブ音源としては以降登場しています。異国情緒あふれるイントロから心を掴まれます。歌謡曲のメロディとノスタルジー溢れる歌詞がたまりません。どことなくインディーズ期の名曲「花屋の娘」を彷彿とさせ、妄想を掻き立てる楽曲です。
秋盤「赤黄色の金木犀」
四季盤においての「秋盤」を担うのが、2004年9月29日発売となった3rdシングル『赤黄色の金木犀』。
美しいギターのアルペジオと、人知れぬ心の昂りを見事に表現した秋の名曲「赤黄色の金木犀」。
秋に香り立つ金木犀の花はオレンジ色・橙色と表現されることが多く、あまり聞き馴染みのない「赤黄色」という色は言葉通り赤みの強いオレンジのことを指します。夕暮れや心象、香りなどの外的要因が合わさって目に映る金木犀の色は確かに「赤黄色」と表現するのが一番美しいなと感じます。
令和に入ってからは酷暑が続いて忘れがちですが、この曲のリリース前年である2003年は冷夏でした。子供ながらにこの頃のニュースでしきりに冷夏という言葉が連呼されていた記憶が思い起こされます。そんな事象を受けて描かれている “冷夏が続いたせいか今年はなんだか時が進むのが早い” という歌詞は自然と自分事のように感じられる効果的な導入なのかもしれません。
赤黄色の金木犀の構成も非常に独特で、Aメロ→Aメロ→サビ→間奏→Cメロ→サビという構成で、全編を通してギターの美しいアルペジオの旋律が耳に残ります。そしてこの曲も間奏からのCメロが至高です。間奏のキーボードソロから“ 期待外れな程 感傷的にはなりきれず ”というCメロに突入していくところで、高まっていくドラムのビート。焦燥感溢れるバンドサウンドがそのまま騒いでしまう胸の内を表しているようで、引き込まれてたまらない気持ちにさせられます。
いつの間にか地面に映った
フジファブリック「赤黄色の金木犀」
影が伸びて分からなくなった
赤黄色の金木犀の香りがして
たまらなくなって
何故か無駄に胸が騒いでしまう帰り道
まさにノスタルジーという言葉がぴったりな、叙情的で美しい日本のギターロック曲なのです。フジファブリックの代表曲は「若者のすべて」でありファンの一人としてもそうだと思いますが、「茜色の夕日」と「赤黄色の金木犀」も外せない代表曲だと感じます。「赤黄色の金木犀」はフジファブリックというバンドを体現している楽曲だとさえ感じます。
秋になるとどこからともなく香ってくる金木犀の香りと共に、どうしても感傷的になってしまう秋という季節。誰しもが感じる郷愁を言語化し、あの言葉にしようのない感傷ごとメロディに落とし込み、静かにしかし劇的に表現した不朽の名曲。この曲に心を動かされない日本人はいない、と言いたいほどに。日本という国の気候がそうさせるのか、日本人に共通する感受性を刺激される曲だと思います。そしてアウトロのアルペジオに良い文学を読んだ時の読後感のような余韻を感じながら曲が終わっていく。金木犀が香ると決まってこの曲のアルペジオが頭の中で鳴るほど、鮮烈な印象を与えられたフレーズでした。
そしてカップリング曲は「虫の祭り」。こちらもアルバム未収録、B面集のみの収録です。
この曲は夏の終わりから秋にかけての物悲しさを感じさせるアコースティックなナンバー。ねっとりとした志村正彦のボーカルが映える情感たっぷりなミドルテンポな楽曲です。ひとりの部屋で居なくなった人を想いながら、部屋の外から聞こえる賑やかな虫の声を祭りや花火に例えた、まるで昭和のフォークソングを想起させるような隠れた名曲です。
冬盤「銀河」
そして四季盤を締めくくる「冬盤」が、2005年2月2日発売の4thシングル『銀河』です。
この曲は当時のフジファブリックをもう一段階上へと引き上げた、現在でもトップクラスの人気曲かつライブ定番曲。変態的かつ奇天烈なポップネスを追求したフジファブリックならではのダンスナンバーです。
まさに予測不可能なUFOの軌道のように、疾走感の溢れるギターのフレーズ。鮮烈な印象を残すイントロから曲の世界に惹き込まれます。現代に存在するあらゆる冬曲の中でもおそらく異色の存在感を放つ「銀河」と言う楽曲は、まさにフジファブリックらしさ全開。春盤〜秋盤まで日本の風景を抒情的に綴った楽曲でフジファブリックらしさを提示してきたところで、バンドが持つもう一つの魅力を遺憾なく発揮しているのがこの「銀河」と言う楽曲だと感じます。「銀河」ももちろん情緒的なメロディや言葉選びを携えていますが、冒頭でも記載した“変態的かつ奇天烈なギターロック”こそもまたフジファブリックの持つ唯一無二であり強烈な個性なのです。変態的というと聞こえが悪いと感じる方も居るかもしれませんが、度肝を抜くような変拍子や不協和音になりかねない転調を上手く操り、プログレやサイケのような前衛的なサウンドを情緒的なメロディと共にポップスに落とし込む大胆さは、最上級の賞賛をこめてそう言い表す他に言葉が見つかりません。この絶妙なバランス感覚が高い中毒性を生み出しているのでしょう。
この楽曲の誰が聞いても奇妙であり気持ちよさを感じる部分が、歌詞の大胆なオノマトペ(擬音語・擬態語)です。
Aメロで “ 二人は街を逃げ出した ” とゆったり不敵に歌い上げた直後のBメロで “ 「タッタッタッタラッタラッタッタッ」と飛び出した ” と、どのように逃げ出したかを教えてくれるわけですが、この破裂音が耳に気持ちいい。文字通りの疾走感と共に、逃避行をする二人の逸る気持ちを演出しているかのようです。
疾走感のあるアップテンポなバンドサウンドに対し、上記のオノマトペ部分以外の歌唱部分はどちらかといえばゆったりと音を伸ばし、志村らしいねっとりとした歌い方をしているのも痺れる部分。冬の寒さで凍てつく静かな真夜中に人知れず起きているドラマを描写している歌詞に見事にマッチしています。
U.F.O.の軌道に乗って あなたと逃避行
フジファブリック「銀河」
夜空の果てまで向かおう
冬の空、澄んだ空気で綺麗に見える星、というロマンチックな光景を歌う冬の歌は昔からありますし定番のシチュエーションですが、そんなシチュエーションを “ UFOの軌道に乗って ” と表現するところがまさにフジファブリックの世界。不思議でインパクト大のフレーズが鮮烈な印象を与え、もう一度聞きたいと何度も思わせる中毒性を生み出します。どこか不思議な世界観だけれど、口ずさみたくなるキャッチーなサビです。
ミュージックビデオも曲のパワーに負けず劣らず強烈な仕上がりです。無表情の女の子が奇天烈な曲をバックに奇天烈なダンスを踊っている。当時はこんなの見たことない奇妙すぎるMVだったからこそ、刺さる人にはめちゃくちゃ刺さったのではないかと思います。深夜に銀河リリースCMが流れた時、家族が寝静まった後の夜更かしをしている自分しか起きていない部屋で、テレビ画面から流れるフジファブリックの世界に釘付けになった感覚を今でも覚えています。
そして銀河のカップリング曲は「黒服の人」。こちらもアルバム未収録、B面集のみの収録です。
フジファブリックの冬の曲、特に雪の曲はどこか物悲しく、降る雪の冷たさすら感じさせるような曲がいくつかありますが、その中でも特に悲しさを携えたロックナンバーです。2009年発売4thアルバム『CHRONICLE』収録の「Stockholm」という楽曲を聞いた時にこの「黒服の人」を思い出しました。「Stockholm」では制作地ストックホルムで静かに降る雪を描写していますが、「黒服の人」では日本の冬の風景とその中で執り行われる別れの光景を深々と描いています。それぞれ制作時期も場所も遠く離れていながら、どこか精神性が似通っている楽曲のように思えます。
総括
フジファブリックは25年間を通して多くの名盤を生み出してきましたし、インディーズ期〜2009年〜2025年という全歴史を通じて語り尽くせないほどのドラマがあります。聞けば聞くほど唯一無二のバンドであることを実感しますし、フジファブリックを聞くことでしか得られない快楽物質があります。世界に溢れる何よりも高い中毒性があるんじゃないか?とすら思います。
個人的に、と言いつつ、おそらくフジファブリックファンならわかっていただける感覚として、四季を感じることという行為の中に、フジファブリックの楽曲を聴くことが含まれているんじゃないかと思うことがあります。四季盤とされているこの4曲は、聴いた人の記憶に深く刻まれ、四季が巡るたびに思い出されるパワーを持った楽曲だと思います。もちろん四季盤以外にも日本の情景や季節を歌った楽曲は多数あり、どれも名曲なので、知らなかったという方がいましたら、ぜひこの楽曲たちをフックにフジファブリックの世界へ足を踏み入れていただけたらと思います。知ってる方々には共感していただけたり、別の解釈として楽しんでいただければ幸いです。
▼脚注 ※末尾の矢印(←)クリックで本文の該当箇所まで戻れます
- 【用語解説】Cメロ…Cメロとはラスサビ(又は大サビ)に向かう前のパートを呼びます。基本的にはポップス・歌謡曲では『イントロ→Aメロ→Bメロ→サビ→2番Aメロ→2番Bメロ→サビ→間奏→Cメロ→ラスト大サビ』のパターンが主で、ラスサビが転調する場合があることも加味し、よりラスサビの感動を増長させ盛り上がらせる演出のためにCメロが組み込まれることが多いです。桜の季節の場合においては、サビ始まりかつ複雑な構成なのでこのパターンに単純に当てはめることはできませんが、ラスサビ前の部分をCメロと呼称させていただいています。 ↩︎
▼参考
フジファブリック Official Website https://www.fujifabric.com