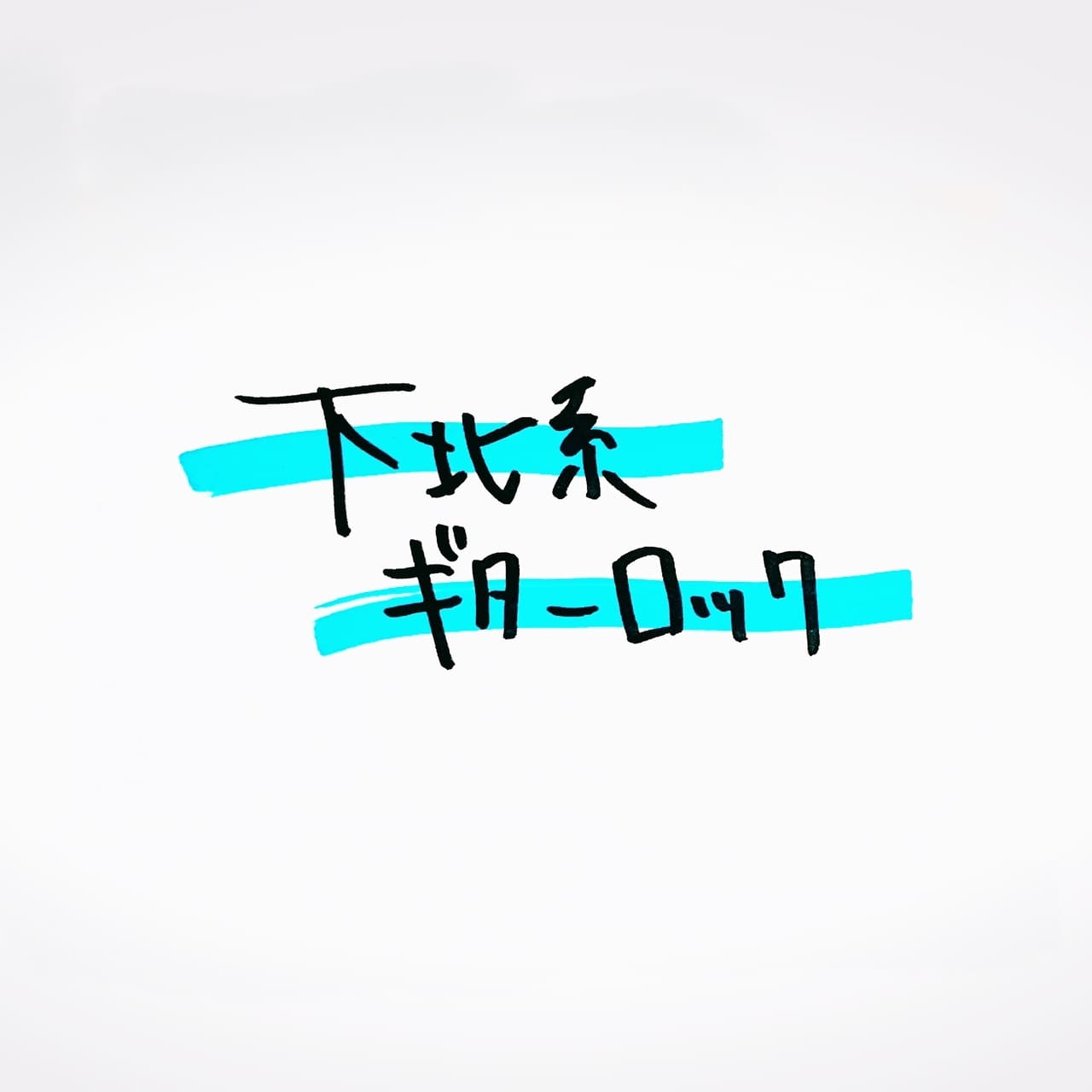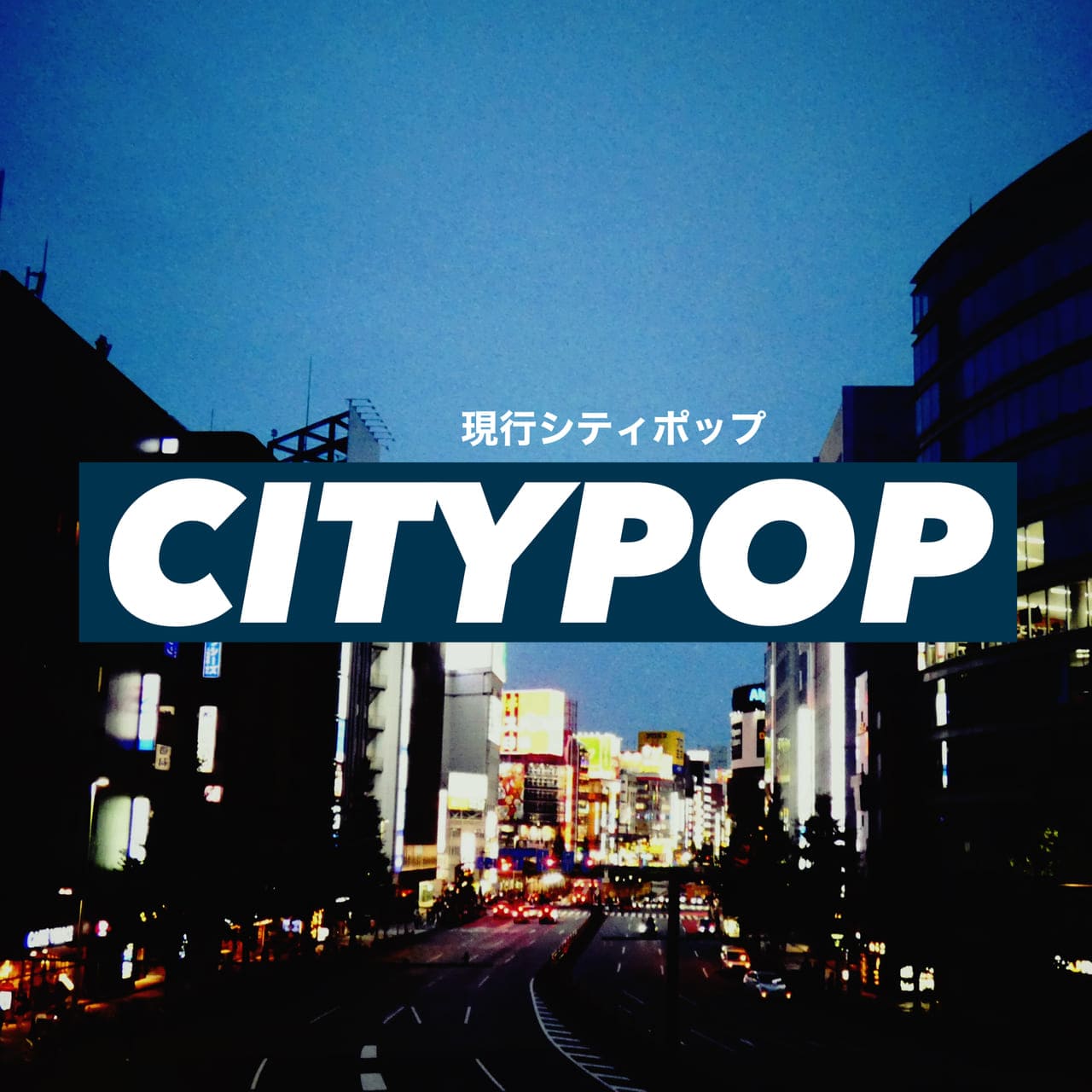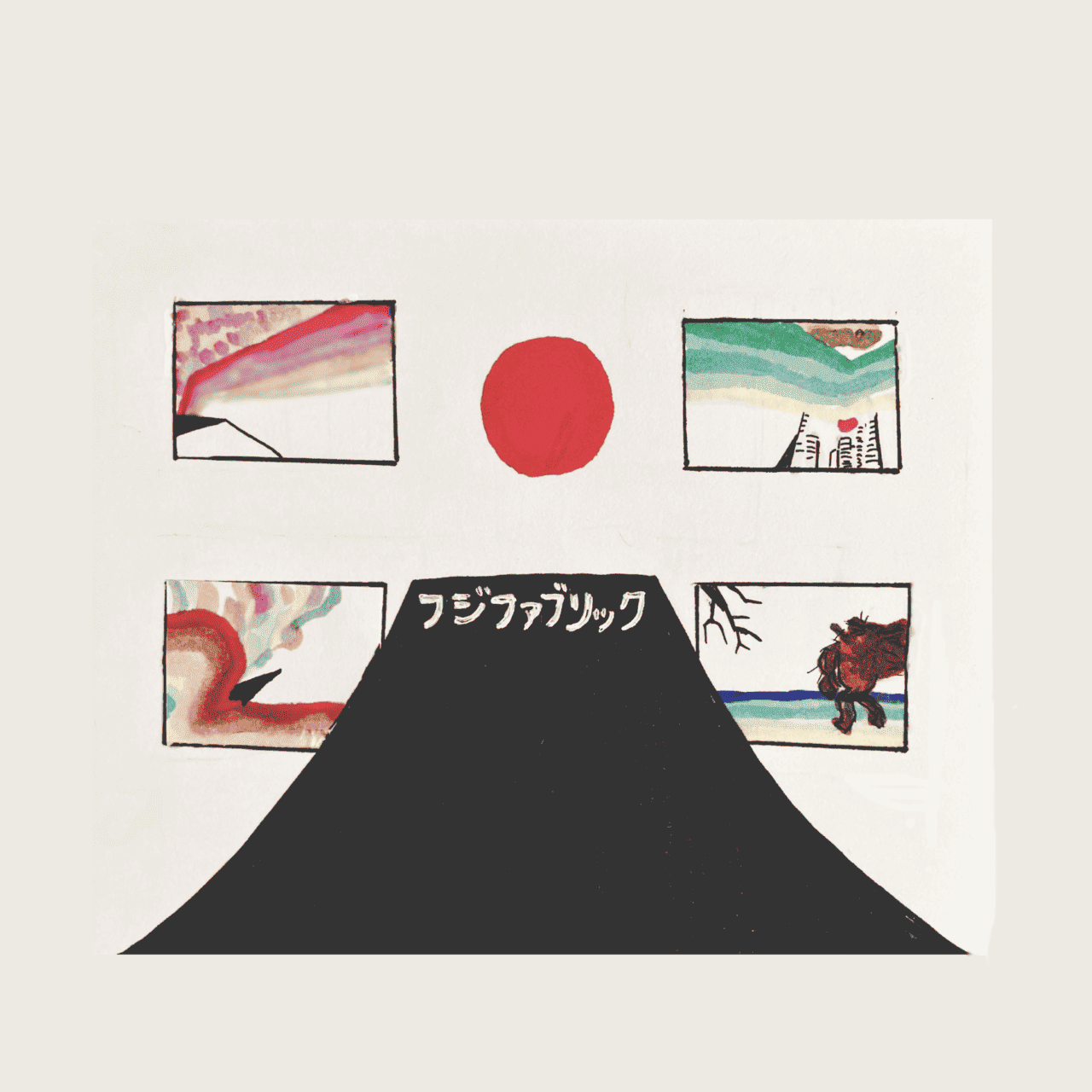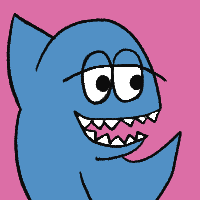
最近聞かなくなったけど、下北系とか渋谷系って言葉があったよね?あれって何だったの?

最近はそういう分類のされ方はあまりしてない傾向にあるけど、90年代初頭から後半にかけては渋谷系、90年代後半から2000年代には下北系ギターロックが流行したね。これは時代の移り変わりと共に音楽のトレンド、そして中心的な発信地が変わったことに由来するよ。今回は下北系に絞って解説していこうか。
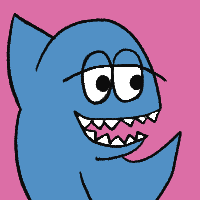
やった〜!じゃあ早速、下北系ギターロックについて解説お願いシャス!
90年代後半〜00年代前半にかけて盛り上がった下北沢の街といわゆる下北系バンド。
説明を求められると意外と難しい“下北系ギターロック”。今記事では下北系ギターロックとは何を指すのか?どういったバンドがいるのか?現在の下北系は?の3点を中心に掘り下げていきたいと思います!
「下北系」下北系ギターロックとは?
下北系、下北系ギターロックが盛り上がったのは90年代後半〜00年代半ば。
90年代中期から後半にかけてピチカート・ファイヴやフリッパーズギターなどの“渋谷系”アーティストが一大ブームを巻き起こします。同じ繁華街、若者の街でも古着屋や小劇場、ライブハウスやレコードショップが軒を連ねている“下北沢”というサブカルチャーの街から盛り上がっていったのが“下北系”と言われるアーティストたちです。
渋谷系が日本のロック・ポップスにHIPHOPやJAZZの要素を含んだどちらかといえばクラブ系のアーティストが多い一方、下北系は音楽ジャンル的にはオルタナティブ・ロックであり、下北系バンドといえばギターロックバンドが大多数。おしゃれで耳心地のいいサウンドの渋谷系に対して、カウンター的とも言える骨太かつ感情的なロックなサウンドはまさにライブハウスから生まれた音楽です。
なぜかというとそれは、下北系ブームを支える大きな二つの理由が二つあるからです。
多くのバンドを輩出したライブハウスの存在
下北系ギターロックを語る上で外せないのが、下北沢のライブハウスの存在です。
下北沢がバンドの街と言われるようになったのは「屋根裏」と「下北沢SHELTER」という二つのライブハウスの存在が特に重要となっています。
1975年に渋谷にてオープンし、THE BLUE HEARTSやRCサクセションを輩出したライブハウス「屋根裏」。1986年に下北沢へ移転してからも渋谷屋根裏の系譜を継ぎ、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTやゆらゆら帝国、スピッツをはじめとする様々なロックバンドを輩出し、注目のライブハウスへ成長していきます。しかし、2015年に惜しまれながら閉店しました。同年、屋根裏の元スタッフ3名がその跡地に「下北沢 ろくでもない夜」というライブハウスをオープンし、かつて屋根裏が呼ばれた“ロックの聖地”を現在も守り続けています。
下北沢SHELTER(シェルター)は1991年、新宿ロフトの姉妹店として下北沢にオープンしたライブハウスです。当時、新宿ロフトの立退き問題(後に和解)が浮上しており、その避難所としてオープンに至ったことから下北沢SHELTERという名前がつけられました。Hi-STANDARDを筆頭にしたメロディック・パンクバンドや、ASIAN KUNG-FU GENERATION、ART-SCHOOLといったギターロックバンドを中心に数々の人気バンドを輩出しています。今も尚、若手バンドの中では“SHELTERワンマン”が憧れの舞台であることは間違いないでしょう。
インディーズレーベル
下北沢がバンドの街と呼ばれるようになったもう一つ大きな理由として、有力なインディーズレーベルが下北沢という地に拠点を構えたことも大きな要因として挙げられます。
まずはレコードショップ兼インディーズレーベルのハイラインレコーズ(HIGHLINE RECORDS)の存在は外せません。1997年に開店した自主制作盤やデモテープを取り扱うCD /レコードショップ。そんなハイラインレコーズが第一弾アーティストとして世に出したのがBUMP OF CHICKENです。1999年3月にデビューアルバム『FLAME VEIN』、そして同年11月にファーストシングル『Lamp』をリリースします。2000年3月にはセカンドアルバム『THE LIVING DEAD』をリリース後、トイズファクトリーからメジャーデビューするまで、バンプのインディーズ時代の作品はハイラインレコーズから発売されています。上記2作のインディーズアルバムは廃盤となり、後にトイズから再発盤が出ていますが、Lampに関しては現在(※2025年3月現在)も再発されておらず廃盤になっています。
そして今もなおインディーズファンなら誰もが知る人気レーベル、UK.PROJECT(ユーケープロジェクト)の存在も大きいです。下北沢に本社があり細分化された子会社レーベルを持っており、下北系を語る上で外せないインディーズレーベルと言って間違いないでしょう。余談ではありますが、後に上述のハイラインもスペースシャワーからUK傘下になります。
UKプロジェクトのアーティストで下北系ギターロックバンドといえば、ART-SCHOOLやBUGER NUDSがまず思い浮かびます。そして、UKプロジェクト傘下の中でも下北系ギターロックのイメージが強いレーベルといえば、2001年に発足されたDAIZAWA RECORDS(代沢レコーズ)。所属バンドとして代表的なのがsyrup 16g、過去に所属したバンドとしてはレミオロメンや椿屋四重奏、THE NOVENBERSといった面々が挙げられます。
下北系ギターロック
ART-SCHOOL
2000年結成。儚くも美しいオルタナティブ・ロック/シューゲイザー1バンド、ART-SCHOOL(アートスクール)。
純度の高いロックサウンドと、映画や文学を彷彿とさせる歌詞。儚く退廃的なボーカルの絶対的な魅力。ギターボーカル・木下理樹の描く生々しくも美しい世界は、生き辛い世の中に苦しむ繊細な人々のシェルターになり続けてきた音楽であると言えます。人間の心にある汚さや弱さも許容して、暗闇の中で同じようにもがき苦しみながら寄り添ってくれる優しさがあります。
マッシュルームカットで線の細い小柄な男性が悲痛の歌声でフライングVを掻き鳴らす。その姿はあまりにも鮮烈でした。邦楽ロックに限った話で言うとギターボーカルの使用するギターはストラトやテレキャスが多いイメージですが、当時このタイプのギターボーカルでフライングVと言えば木下理樹ぐらいしかいなかった印象です(今でもそうかもしれません)。フライングVというギターはハードロックやメタルのイメージが強いので、なおさらそのギャップで印象的なスタイルでした。
ART-SCHOOLは現在に至るまでメンバーチェンジや活動休止を乗り越えてきましたが、初期ART-SCHOOLのメンバーは現ストレイテナーの大山純、日向秀和、そして現ランクヘッドの櫻井雄一と、テクニック・存在感・センス抜群のメンバーばかり。その後は戸高賢史の加入、宇野剛史・鈴木浩之の加入・脱退を経て、現在は木下理樹・戸高賢史の二人体制で、サポートメンバーとしてNUMBERGIRLの中尾憲太郎、MO’SOME TONEBENDERの藤田勇、ニトロデイのやぎひろみが参加し活動しています。木下理樹という普遍的な軸がありながら、体制によって違った色を感じられるのもまたART-SCHOOLの魅力と言えるでしょう。
2002年11月、東芝EMIより発売されたファーストアルバム『Requiem for Innocence』は、アートの初期衝動を詰め込んだ名盤オブ名盤。フルアルバムの中で唯一この作品のみがずっとサブスク配信されていなかったのですが、2024年6月19日からサブスク解禁。個人的で勝手な話ですが、実家にいた頃から家を出て現在に至るまで肌身離さず大事にしているアルバムのひとつなので、特別な存在でいてほしかったという複雑な気持ちもありました。ですが、この作品が時代に埋もれていってしまうのはあまりにもったいない。衝動を携えた疾走感のあるポップソングから救いを求めて囁くように歌う美しいロックバラードまで、アルバムの頭から最後まで通してART-SCHOOLの魅力を余すことなく味わえる作品。1曲目の1音目から惹き込まれ、その瞬間からその場を離れることは許されないような緊張感と圧倒的な存在感で心を奪われ続けている1枚です。2023年のレコードの日2には1stと2ndがアナログ盤で発売されたのも物凄く嬉しいニュースでした。今もなお多くのファンに愛され続けている名盤です。
syrup16g
1996年結成、2008年解散。2014年再始動。ダウナーで厭世的な歌詞世界と美しきメロディが絡み合うスリーピースロックバンド、syrup16g(シロップ16グラム)。
syrup16gに出会ったことで救われた人や、自分の存在を肯定することができてこの世にいられている人も多いんじゃないでしょうか。それくらいsyrup16gの描く世界は人間の心の弱くて脆い部分を描いていて、危うくも美しい世界が広がっている。しばしば鬱ロックと称されることがありますが、その言葉だけで括ってしまうのは乱暴なのではないかと常々思います。確かに健康的で正気でいられる人には響かない音楽ですが、それは傷つきやすい無垢な心で人間の本質を歌っているからこそ。ギターボーカル・五十嵐隆の書く詩世界は、彼の目で見て感じたことを彼なりの哲学を交えながら表現していて、説教くさくもなく同情を誘うでもなく、端的に心を刺してきます。歌詞もメロディも美しいので、憂鬱や焦燥の中にあってもsyrup16gを聴きながら深く静かな闇に落ちていくことで、安心できる日が多く作れるのではないでしょうか。
syrup16gは2006年8月23日に2枚のベストアルバム『動脈』『静脈』を出していて、こちらの2枚をまずは聴いてみるのがオススメです。ですが今回ご紹介したいのは、2001年発売インディーズ1stアルバム『COPY』。syrup16gの代表曲を選ぶのが難しいですが、もし1曲だけ選べと言われたら「生活」だと思っています。
君に存在価値はあるか
syrup16g 「生活」
そしてその根拠とは何だ
涙ながしてりゃ悲しいか
心なんて一生不安さ
実際に『COPY』のCDの帯にはこの曲のパンチラインを引用し「君に存在価値はあるのか」としていたのでその印象も少なからずあるのかなとは思うのですが、この楽曲は誰もが思っていて言えなかった真理を突いていると感じた衝撃の楽曲でした。非常に強い言葉で言い切っているのですが、五十嵐隆のどこか気怠く脱力感のある歌声が聴き心地が良くて何度聴いても飽きが来ません。そもそもの楽曲の中毒性も高ければsyrup16gのようなバンドは他になく、真似をすることも到底不可能なので、正真正銘、syrup16gでしか得られない音楽がここにあります。
BUGER NUDS
1999年結成、2004年解散。2014年より復活を遂げた、知る人ぞ知る名バンドBUGER NUDS(バーガーナッズ)。
ギターボーカル・門田匡陽が紡ぎ出す物語は、悲しくも美しい。ひりつくような焦燥感を携えた鋭利なサウンド。冬の明け方のように澄んだ美しいメロディ。どこか皮肉を感じさせながらも決して諦めていない、命を燃やしながら存在証明をしていると感じるような、鬼気迫るロックがここにはあります。
所属レーベルはTELESCOPE-LABEL(独立レーベル/流通はUK.PROJECT他)。2014年の再結成に至るまでは既発作品が全て廃盤となっていましたが、2014年に廃盤5タイトルを復刻。そしてなんと2024年5月には過去作品が待望のサブスク解禁。廃盤で入手困難だった時期が長かった名作アルバムゆえに知る人ぞ知る存在でしたが、長い年月を経てついにこの日がやってきました。
まず何を聴けば?という方には『LOW NAME』『線』、『自己暗示の日』『kageokuri』、『symphony』の5作のアルバムをそれぞれ3作品にまとめた2014年の復刻3タイトルが手を出しやすいんじゃないかなと思います。どの作品にも思い入れの深い好きな曲があって優劣つけ難いので、いつかまた別の記事でBUGERNUDSを語れたら。
EMO /インディーロックの影響も感じさせる至高のオルタナティブロック。スリーピースならではのシンプルなバンドサウンドながら、それぞれの個性を最大限に引き出していく秀逸なフレーズの数々は聴く者の心を掴んで離しません。まるで夜の闇の中から一筋の光を見つけ出そうとするような音楽は、この先も孤独な誰かを救い続けていくでしょう。
LUNKHEAD
1999年結成。どこまでも青く内なる情熱を燃やすロックバンド、LUNKHEAD(ランクヘッド)。ギターボーカル・小高芳太朗の燻り続ける熱を放出するような尖った感性と、広い世界での孤独を拾い上げるような優しさを持ち合わせている珠玉の楽曲たち。不器用で等身大だからこそ愛おしいし救われる。時折襲われてしまうどうしようもない焦燥感にマッチする前のめりなサウンドとノスタルジーが漂うロックこそがLUNKHEADの武器であり魅力だと感じます。
愛媛県の高校の同級生同士で結成。それぞれが上京した後、下北沢のライブハウスを中心に地道な活動を続け、2003年に自主制作盤1stマキシシングル「千川通りは夕風だった」をタワレコ及びハイラインレコーズで販売。2010年には脱退したドラマー石川に代わり、親交のあった元ART-SCHOOLの櫻井がサポートとして加入。その後正式メンバーになり、現在に至ります。
20年以上のキャリアでフルアルバムだけでも13枚出している(2025年3月現在)ので、彼らの魅力を紹介できる作品を一つに絞るのは苦渋の決断すぎる。LUNKHEADに出会った頃の作品はどれも感情が乗ってしまうし、1枚なんてとても選べない。となると、2008年3月発売『Best Album「ENTRANCE 〜BEST OF LUNKHEAD age18-27〜』について言及したくなってしまいました。なぜこのベスト盤を選んだかといえば、新曲として1曲目に収録されている「ENTRANCE」がめちゃくちゃ好きだからに他ならないのですが、初期・中期ランクヘッドのアルバムを聴いてきたファンとしての目線から見ても、「白い声」や「体温」〜ポップ色の強い「カナリアボックス」まで、彼らの魅力を多面的に味わってほしいという意味でも外せない楽曲がしっかり入っていてバランスのいい1枚だと思います。
大手レコード会社にありがちなバンドに許可なく勝手にベストアルバムの発売が決まってしまったという経緯3がありながらも、それを逆手にとってこの素晴らしい作品を作りあげたLUNKHEADの熱意溢れる1枚。
もちろんベストアルバムというのはバンドの入口でしかないので、良いなと思ったらその先の世界の扉を一つ一つ開けていってほしいと願っています。
ASIAN KUNG-FU GENERATION
1996年結成。日本の音楽シーンに今もなお多大な影響を与え続け、時代を牽引し続けるギターロックバンド、ASIAN KUNG-FU GENERATION(アジアンカンフージェネレーション)。90年代オルタナやインディーロックの香りが漂うロックサウンドと、ギターボーカル・後藤正文(通称:ゴッチ)の独自の視点から描く世界は唯一無二。時に焦燥感に溢れ、時に達観した視点で世界を切り取り、時に感傷的なフレーズを用いて人の心へ染み込んでいく。確固たる哲学を持ってロックンロールバンドであり続けていることが、多くのロックバンドやアーティストを筆頭に、平成を生きてきたロックファンの支持を得てきた理由であると言えるでしょう。
ASIAN KUNG-FU GENERATION(略称はアジカン、AKGなど)は大学の音楽サークルにて結成された四人組ロックバンド。出身大学は関東学院大学で、最寄り駅は神奈川県の金沢八景。アジカンのコンセプトアルバムに『サーフ ブンガク カマクラ』という江ノ電の駅名を冠した楽曲で揃えた作品があるように、彼らにとって横浜は縁の深い地でもあります。が、90年代後半といえばパンク/メロコアブームの全盛期であり、F.A.D YOKOHAMAをはじめとする横浜のライブハウスはパンク系バンドが強かったのもあり、出演権を求めてオーディションを受けているうちに下北沢へと行き着いた経緯があります。そうしてアジカンが世に出るきっかけとなったライブハウスがまさに下北沢SHELTERであり、初ワンマンライブはもちろん、凱旋ライブも行うほど思い入れのあるハコなのです。
2003年発売ファーストアルバム『君繋ファイブエム』は、初期衝動と自己表現力の高さの両方を併せ持った平成音楽史に残る名盤。もちろん続く『ソルファ』も『ファンクラブ』もそれ以降の作品も名盤であることは間違いないんですが、アジカンというのはこういうバンドなんだ、というのを明確に示し、CDを手に取った人全てを圧倒したエネルギーのある作品だと思います。1曲目「フラッシュバック」のイントロが流れるたびに、いつだってCDプレイヤーで再生したあの日へ引き戻されてしまう。現在の説得力のある歌声も素晴らしいですが、この頃のゴッチの気怠さを携えた荒削りなボーカルがまた楽曲の疾走感に合っていて最高なんですよね。フラッシュバック〜未来の破片の繋ぎはいつ聴いてもワクワクします。曲順・曲間含めて全曲通して隙がない傑作アルバム。個人的にはアジカン史上一番ロック色の強い作品なんじゃないかと感じています。
BUMP OF CHICKEN
今や幅広い世代から愛され続けるロックバンドBUMP OF CHICKEN(バンプオブチキン)。
ギターボーカル・藤原基央が作り出す物語性の強い歌詞世界と、キャッチーで心を打つメロディ。多くの孤独で迷える少年少女を救ってきたはぐれ者のためのロックンロールは、どれだけバンドが大きくなっていっても、一番近くで鳴ってくれているような優しさに満ちている。彼らのロックはジャンルの枠に収まることのない、BUMP OF CHICKENにしか奏でられないロックであると言えるでしょう。
1994年結成。千葉県佐倉市出身で、メンバーは幼稚園からの幼馴染バンドであり、中学時代に再会後、紆余曲折を経て現体制へ。1996年に現メンバーとなり、BUMP OF CHICKENが誕生します。当初は地元・千葉で活動を続けながら、前項(インディーズレーベル項参照)のハイラインレコーズでデモテープを販売しながら知名度を伸ばしていきます。そういった縁もあって、ハイラインレコーズのある下北沢を中心に都内に活動を広げていき、千葉から下北沢へ、下北沢から全国へと知名度を着々と広げていきました。
ハイラインレコーズから発売された1999年3月デビューアルバム『FLAME VEIN』。後にトイズファクトリーからメジャーデビューする際に、廃盤となっていた今作は2004年に再発盤『FLAME VEIN +1』として、同じく廃盤シングル『Lamp』のカップリング曲である「バトルクライ」を追加収録して発売されました。この作品の歌詞カードが全て手書きで、CDを聴いた時の体験としてはすごく印象的だったのを覚えています。藤原基央の所々掠れたような独特な歌声と、温かみのある手書きの文字が“生”を感じさせてより一層心を打たれました。今作には「ガラスのブルース」や「アルエ」といった初期のバンドとしてもファンにとっても思い入れが深い特別な楽曲が収録されています。個人的には「ノーヒットノーラン」が今もよく口ずさんでしまうくらい好きな曲。囁くような歌い出しからサビに向かって盛り上がっていく感じが気持ちいい曲です。
ACIDMAN
1997年結成。生命や宇宙をテーマにした壮大な世界を歌い続けるスリーピース・ロックバンド、ACIDMAN(アシッドマン)。パンクやジャズ、ボサノヴァといったジャンルも取り入れながら、遊び心がありつつも硬派なギターロックサウンドが魅力。彼らの音楽で広がっていく世界はまさに宇宙。ギターボーカル・大木伸夫の知識に基づいた哲学というべきか、考えや主張が綴られた歌詞は美しく響きながらも考えさせられます。スリーピースでありながら骨太なロックサウンドで、見る者聴く者を圧倒させる力のあるバンドです。
出会いは埼玉県の私立高校の軽音部。1999年にボーカルが脱退し、大木がギターボーカル及び作詞作曲を担うようになり現体制のスリーピースバンドに。インディーズ時代は下北沢を中心に活動し、初ワンマンは2002年5月に下北沢GARAGE(2021年閉店)でした。その後は日本武道館を6回成功させ、今年2025年10月26日には7年ぶり7度目の日本武道館ライブも控えていたり、地元埼玉県では主催フェス「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI”」を開催するなど名実ともにロックバンドとして確固たる地位を築き上げています。
2002年発売ファーストフルアルバム『創』は初期ACIDMANの不朽の名盤です。今作品で東芝EMIからメジャーデビューを果たしますが、発売に先駆けて「造花が笑う」「アレグロ」「赤橙」の冒頭を彩る3曲がプレデビュー・シングルという位置付けとはいえ300円という破格の値段でリリースされていたというのも驚きの話。特に「赤橙」はインディーズ時代の2000年11月にもシングルとして発売しており、メジャーでもシングルカットされるなどACIDMANを象徴する代表曲でもあります。まるで海外文学のような美しく壮大な歌詞とメロディ、静と動を巧みに操るサウンド、抑揚の効いた歌唱。どれを取っても心地よい名曲。当時もめちゃくちゃカッコいいなと思って聴いていましたが、歳を重ねるごとにACIDMANというバンドの持つ魅力や格好良さが尋常じゃないことに改めて気付かされます。
椿屋四重奏
2000年結成。歌謡曲を感じさせるメロディとロックサウンドが融合した強烈な個性を放つロックバンド、椿屋四重奏。和の要素が強い楽曲が持ち味で“艶ロック”とも称されています。2010年12月31日をもって解散を発表。ギターボーカル・中田裕二は解散後もソロ活動を続けています。20周年を超えた近年では、限定的にツアーを含むライブ活動で再集結を果たしました。
椿屋四重奏は駆け出しの時代、音源をハイラインレコーズに置いてもらっていたり、ライブ活動も含めて下北沢にて活動をしていました。個性的で唯一無二のスタイルから噂が広まり、2003年からUK.PROJECT(DAIZAWA RECORDS)所属になります。インディーズ1stとなる2003年8月発売ミニアルバム『椿屋四重奏』では初期衝動を感じさせながらもすでに妖しく危なげな魅力は炸裂しており、独自のスタイルが確立されていたことが窺えます。その約8ヶ月後の2004年4月にはファーストフルアルバムとなる『深紅なる肖像』をリリース。歌謡曲とロックの塩梅がより絶妙になり、侘び寂びを感じさせるメロディと骨太なロックサウンド、情景が浮かぶ艶やかな歌詞で、日本のロックの新たな可能性を当時のシーンに叩きつけた1枚です。
椿屋四重奏初期の2枚も外せないんですが、やはり“椿屋四重奏”というバンドの魅力が最大限に詰まっているんじゃないかと感じるのが、2005年9月発売セカンドアルバム『薔薇とダイヤモンド』。インディーズ時代最後のアルバムであり、今聴いても色褪せることのない名盤だと思います。まるで踊っているみたいなサウンド。和と言っても大正時代や明治時代のように、和の中に洋を取り込んだモダンな印象を受けます。歌謡曲のメロディと抒情的かつ文学的な歌詞に、情感豊かなギターロックサウンド。圧倒的な華と艶やかな歌唱、唸るフレーズの数々。気付いた時には椿屋四重奏が作り出した世界の中に没入させられてしまっているはずです。
フジファブリック
2000年、山梨市富士吉田市にて結成。叙情的で郷愁を誘うメロディと予測不可能な展開で独自の世界観を構築するギターロックバンド、フジファブリック。ギターボーカル・志村正彦を中心に結成、インディーズ時代からメンバーチェンジを重ね、2004年、現メンバーを含む5人体制でメジャーデビューを果たしました。
2009年12月24日、ギターボーカルでありフジファブリックの核であった志村正彦が急逝。後に、残されたメンバーである山内総一郎、加藤慎一、金澤ダイスケの3人体制で活動を継続してきました。この時、フジファブリックというバンドを存続させてくれたことで、当時を知らない人たちにもフジファブリックの楽曲が届けられ広く愛されるようになったのではないかと思います。そんな彼らが今年、2025年2月をもって活動休止を発表しました。今までもこれからも、唯一無二の素晴らしいロックバンドであることは変わりません。
高校卒業後、山梨から上京してきた志村は高円寺に住み、高円寺のライブハウスで氣志團のメンバーと共に働いていた過去があります。名曲「茜色の夕日」のシングルのジャケットになっている写真が志村正彦が撮影した高円寺陸橋の写真なのも、歌詞の内容も相まって一層胸が熱くなります。初期フジファブリックにおいて、彼ら自身はもちろんファンの中でも思い入れの深い特別な一曲。全国区になる前のフジファブリックは高円寺・中野エリアはもちろんですが、SHELTERやCLUB Queといった下北沢のライブハウスにも多く出演していました。
インディーズ時代のアルバムは『アラカルト』と『アラモード』の2作。
2002年10月発売1stミニアルバム『アラカルト』収録時は志村正彦を除く他のメンバーが入れ替わる前のメンバーで録音されています。その後、2003年6月に発売される2ndミニアルバム『アラモード』は、金澤ダイスケと加藤慎一加入後の作品となります。一曲目の「花屋の娘」は志村節全開。哀愁やノスタルジーを漂わせながらも、妄想を加速させていく歌詞。ねっとりと絡みつくような質感が中毒性抜群です。
後にメジャーデビュー前のプレ・デビュー盤として『アラカルト』と『アラモード』から7曲をピックアップして再録した2004年2月3rdミニアルバム『アラモルト』が発売されることになりますが、残念ながら既に廃盤作品。後に生産限定盤のFAB BOXに収録されますがこちらも廃盤になっています。長年フジファブリックに心酔しきっているファンからしてみると全作名盤なのですが、インディーズ時代の作品はただでさえ強烈な個性の生身感が良い意味で強く、哀愁と奇天烈が同居している様をまざまざと見せつけられているようなところが好きです。
メレンゲ
2002年活動開始。浮遊感のある柔らかいメロディと美しい情景描写が魅力のギターロックバンド、メレンゲ。
当初はギターボーカル・クボケンジのソロユニットとして活動を開始し、2003年にはスリーピース体制に。2015年にドラムのヤマザキが脱退し、現在はベースのタケシタツヨシと二人体制になり、サポートドラマーを迎えながら活動を継続しています。
フジファブリックと同様、SHELTERやCLUB Queを始めとする下北沢のライブハウスや、新宿LOFTなどを中心にライブ活動を広げていたメレンゲ。特に春になるとメレンゲが聴きたくなります。優しくて切ないメロディ。当たり前のことがこんなにも美しいのだと感じることができる繊細な心。傷つきやすく脆い。ただその表現方法は素直なようで素直じゃなくて、一筋縄では行かないような感じ。だからこそ、コアな音楽ファンの心を掴み続けているのではないでしょうか。
2006年4月発売ファースト・フルアルバム『星の出来事』。
このアルバムが出た頃にメレンゲのことを知り、1曲目「カメレオン」から心を掴まれました。カメレオンという曲は恋愛や風景描写ではなく風刺的で自己内省的な側面を持つ楽曲なので、当時のメレンゲの中で言えば異色な曲なのですが、自己同一性に悩んでいた思春期の自分にはかなり強烈に響きました。この名曲を1曲目に持ってきたこのアルバムには、「君に春を思う」や「アオバ」「すみか」といったメレンゲの真価を発揮している美しいメロディに浸れる名曲多数収録。「君に春を思う」の歌詞にある“この星のまん中 嘘みたいに本気で 愛している ありえないよな”という歌詞はまさにメレンゲ!という感じがして好きです。素直すぎるラブソングは何だか綺麗すぎて苦手に感じてしまう時があるんですが、そういう人にこそぴったりなバンドだと言えます。
余談ですが、フジファブリックと似たような時期に下北沢を中心に活動をしており、志村正彦とも特別な親交があったクボケンジ。アウトプットの方法は違うけれど、この二人が仲良くなるのは必然だったのかなと思えます。
下北系ギターロックのその後
基本的に下北系ギターロックといえば、90年代後半〜00年代のバンドのことを指しています。
下北系ギターロックという括りで呼ばれていた若手バンド達が成長を遂げて次第に全国区になっていき、「下北系」という括り以外にも「ロキノン系」や「邦ロック」という広義で使える呼び名で括られることが多くなっていったことと、“下北系”という言葉自体が、下北沢をまつわるカルチャーを含めこの時代のムーブメントを表す言葉としても用いられていたことが大きな要因と言えるでしょう。
とはいえ、その後も前述の世代の下北系ギターロックに影響を受けたバンドや、KEYTALKのように下北沢を中心に活動するバンドたちは次々に登場しています。彼らが何と呼ばれているのかといえば、もちろん“下北系”と呼ばれたり、同義ですが“下北発”という形で紹介をされ、今もなおインディーズファンに注目され続けています。
総括
00年代〜10年代に学生時代があった世代なので、音楽の目覚めは下北系ギターロック直撃世代でした。バンプやアジカン、エルレからロックを聴き始め、フジファブリックに出会ってからは、後にも先にもこんなに夢中にさせられたバンドはいないというくらい心の支えになっていました。それは現在進行形です。多感な時期に聴いたというのもあって、この世代のバンドには音楽観はもちろん、人生観にも多大な影響を受けてきたと思います。本当は全バンド全アルバム語りたいくらいでしたが、下北系ギターロックに絞った結果、こういった10組を紹介させていただきました。同世代や下北系ギターロックファンには共感していただけたら幸いです。もし知らないバンドがいたらぜひこの機会に聴いていただけたら嬉しい。今回紹介したバンドは長年聴いてきても飽きが来なかったどころか年々好きになっていくバンドたちばかりです。
下北沢という街は、ライブハウスはもちろん古着屋だったり、ディスクユニオンやJET SETを始めとするレコードショップが立ち並ぶ雑多な街。渋谷や新宿ほど都会ではない、高いビルなんてない。田舎すぎず、孤独なようで孤独ではない。そんな街だからこそ、どこかうまく社会に馴染めない私たちを救ってくれる音楽が日々生まれていくんだろうなと思います。
▼脚注 ※末尾の矢印(←)クリックで本文の該当箇所まで戻れます
- 【ジャンル解説】シューゲイザー(Shoegazer)…ロック、特にオルタナティブ・ロックにおける音楽ジャンルのひとつ。90年代初頭イギリスの新人ロックバンド、ムースの記事で、足元の歌詞カードを見る姿を揶揄した「Shoe(靴)+Gazer (見る人)」と言うのが始まり。その後は、エフェクターを多用するため足元のペダルボードを見る姿を表したと言う意味に転じている。サウンドとしては、エフェクターで歪ませた轟音のギターとフィードバックノイズ、切なく甘いメロディが特徴。 ↩︎
- 【用語解説】レコードの日…元々は日本レコード協会が1957年に制定した記念日。レコードは文化財であるという理念のもと、文化の日である11月3日を「レコードの日」と制定しました。このレコードの日にあわせて、アナログレコードのプレスメーカーである東洋化成株式会社が企画して、全国のレコードショップでアナログ新品注目タイトルが多数販売される「レコードの日」というイベントを毎年開催しています。
公式サイト▶︎https://record-day.jp
↩︎ - 【もっと深掘り】許可なく勝手にベストアルバムの発売が決まってしまったという経緯
LUNKHEADのオフィシャル曲解説ブログにて経緯が語られていましたので詳しくは下記ご参照ください。
→https://lunkhead.site/blog/song-commentary/503/ ─ LUNKHEAD official Site「LUNKHEAD曲解説ブログ」 ↩︎